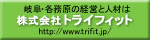|
|
|
|
2002
12.08 |
知ったかぶり経済学(3)<失業率5%をどう考えるか>/サンタクロース/11月の岐阜新聞・チラシ状況
|
|
知ったかぶり経済学(3)<失業率5%をどう考えるか>
現在、日本の失業率は5%を超えています。(今年10月の完全失業率は5.5%で過去最高。ちなみに10年前の1992年は2.2%でした。) マスコミでも大きくとりあげられているので、ご存じの方も多いでしょう。 失業率5%と言われてもちょっとピンときませんが、20人に1人は働きたくても働き口が見つからない状態と表現すると分かり易いかもしれません。 さて、先日、失業率についてある知人がこんなことを言っていました。 「自分の職場で成績が20番目の人を思い浮かべて、その人が給料に見合うだけの働きをしているかっていうとそうでもないよね。だから5%は許容範囲内だ」。 いささか極論だとは思いますが、もし本当に成績順で20番目の人が選ばれているのなら、真面目にやっている人がそれほど失業を恐れる必要はなさそうです。 しかし現実には、20番目の人が選ばれているかどうかが怪しくて、20人に1人がランダムに当たるくじ引きをやっているように感じられます。 そうすると深刻度がぐっと増してきますね。 ではそこで、20分の1のくじ引き状態の不安を解消するには、どんな手が考えられるでしょうか? 方法は2つあります。 ひとつは、20分の1の確率を引き下げて25分の1とか30分の1とかにすること。 これは、誰に当たるか分からないから、皆で我慢して堪え忍びましょうという考え方。 もうひとつは、20番目の人がちゃんと選ばれる仕組みを作って、全体の効率性を上げること。 これは、なあなあをやめて、結果は不平等でもフェアな競争をしましょうという考え方。 皆さんは、失業率5%時代を乗り切るには、どちらの方法が有効だと思いますか?(F) サンタクロース 皆さん、サンタクロースしっていますよね、でも、説明してくださいと言われると困ってしまいますよね、そこで、少し調べて見ました。 むかし、ミラ(現在のトルコ)に、ニコラスという人がいました。 ニコラスはキリスト教を信じて、人々にその教えを広めていました。 あるとき、町に貧しくて娘をお嫁にだせないという人がいるのを知り、ニコラスは、その人の家に窓から金貨を投げ入れてあげました。 次の日、金貨を見つけたい家の人は喜んで、娘をお嫁に行かせました。 このことが町中に広まり、ニコラスは人々から尊敬されるようになりました。 その後、ニコラスは、セント(聖)・ニコラスと呼ばれるようになり、キリスト教がアメリカに広まっていくなかで、「セント・ニコラス」がなまって「サンタクロース」と呼ばれるようになりました。 それから、このニコラスが窓から投げ入れた金貨が偶然、暖炉の側につるしていた靴下の中に入ったことから、クリスマスプレゼントを靴下の中に入れる習慣ができました。 ちなみに、サンタクロースの赤と白の服は。 1931年、アメリカのコカコーラ社が、冬の販促キャンペーンにサンタクロースを起用。 その広告でハッド・サンドブロムという画家が描いたのが始まりです。 それまでのサンタクロースはコートやマントを着ていて、特に決まった色はありませんでした。 11月の岐阜新聞・チラシ状況 11月合計・511枚 平均17.0枚 1.スーパー・102 2.パチンコ・46 3.住宅・29 曜日平均 日・11.5 月・8 火・14.2 水・13.2 木・20.5 金・18.4 土・29.8 (なべ) |
|
|
|
|
|
2002
11.24 |
IT時代なのに/日本の失業者/一粒百行
|
|
IT時代なのに
「情報を共有し情報の統一を図るためには、ダイレクト・コミュニケーションに勝るものはない。 コンビニ業界では情報が命であるからこそ、私はダイレクト・コミュニケーションにこだわる。 本部での会議に自ら足を運び、大きな情報源である経営者と直に接することにより、自分なりに情報を吸収し、膨らませていく。 そして、現場に戻り、今度は一人ひとりのオーナーとダイレクト・コミュニケーションを行う。 私が仮に一時間かけて話しても、オーナーに話すときには三分の一か五分の一になるかもしれない。 それでもダイレクト・コミュニケーションの方を私はとります」この内容でお解りいただけたでしょうか。 ご存じコンビに業界NO.1。セブンイレブンの鈴木会長の言葉です。 セブンイレブンのFC会議の話です。 毎週火曜日、現場の店舗で経営指導やアドバイスにあたる1200人のオペレーション・フィールド・カンセラーが集まります。 日本全国から集まる費用は、30億円。POSシステムによる徹底した管理の会社としては、時代錯誤のように感じられるが、それほどまでに、直接会うことが大切なのでしょう。 世の中が進めば進むほど、情報は価値が増していくでしょう。 そして、ITを駆使して伝達されるでしょう。 しかし、価値ある情報は、どんな時代も人から発信されるのではないでしょうか?(なべ) 日本の失業者 現在、日本の失業率が5.4%と言われています。 数値として表すと、実際そうなのかもしれません。 しかし、果たして、全員が本当の失業者なのか疑問に思います。 仕事柄、ハローワークに行く機会が多いのですが、確かに、仕事を探している人で大変混みあっています。 そんなに仕事がないものなのか、私も実際、ハローワークの専用端末機で見てみました。 求人は予想通り、いえ、それ以上にたくさんありました。 では、なぜ仕事が決まらない人が多いのでしょう。 明らかな理由が二つあると思われます。 まず一つは、自分の希望する職種、待遇がない。 そしてもう一つは、生活するのにそれほど切羽詰っていない。 後者の理由が大部分を占めるでしょう。 新卒の就職率低下も、企業の求人数が減ったのも理由でしょうが、それ以外にも、定職を持たなくても・・・という人が増えた理由もあるでしょう。 若い人がそう思っているだけでなく、その親も、別に無理に働かなくてもいいと言う人もいるそうです。 そうです。日本では、働かなくても生活はできてしまいます。 昨年行ったインドでは生活するために必死でした。 仕事をしたくてもできない、学校に行きたくても行けない。 毎日、その日に食べるものを得るのがやっとという人達も多いのです。 環境的に日本は、非常に居心地がいいのですが、本当にこれでいいのでしょうか。 10年、20年後がどうなっているのか、楽しみのような、不安なような、複雑な心境です。(あん) 一粒百行 「一粒百行・いちりゅうひゃっこう」という言葉を知っていますか。 NHKの大河ドラマ「利家とまつ」の中で、使われた言葉だそうです。 私もある著書を読んで最近知りました。 意味は「一粒の米を作るにも、百の手間がかかる」という意味です。 私も経営コンサルタントをしていて、この言葉が、本当に胸に沁みました。 厳しい経済状況の中、伸びている企業は、たゆまない影の努力があります。 そういう努力がありはじめて企業は成長していきます。 私もこの言葉に出会えた事に感謝し、心の糧として使わせていただことうと思いました。(なべ) |
|
|
|
|
|
2002
11.08 |
91歳の教え/高校生の優しさに出会えて、ハッピーな気分になった/10月の岐阜新聞・チラシ状況
|
|
91歳の教え
日野原重明さんと言えば、今、書店の注目度1番ではないでしょうか? ご存知、聖路加国際病院の理事長さんで現役のお医者さまです。 私も日野原さんの本を2冊読みました。 「生き方上手」「生きるのが楽しくなる15の習慣」です。 その二冊で共通して感じた事は、人はいかに習慣が大切であるかを感じました。 よい習慣を、身につければ成功します。 病気も習慣からくるのが非常に多いそうです。 ですから、生活習慣病といわれます。 経営者も、経営のよい習慣を身につけていれば、成功する可能性が高いと思われます。 その一つに朝が強い経営者は、成功している人が多いように思います。 「生きるのが楽しくなる15の習慣」最後に次のように書かれています。 「鳥は飛び方を変えることはできない。 動物は這い方、走り方を変えることはできない。 しかし、人間は生き方を変えることができる。 繰り返す毎日の行動を変えることにより、新しい習慣形式により、新しい習慣の選択を人間は決意できる。 人間には選択の自由がある。 そして、意志と努力により新しい自己の形成することができる。 それは、人間と動物とを根本的に区別するものといえよう。」経営も同じだと思います。 「意志と努力により新しい自己の形成することができる」21世紀はそういう経営者が勝っていくでしょう。(なべ) 高校生の優しさに出会えて、ハッピーな気分になった 阪神タイガースの監督、星野仙一さんの講演会で、僕はすごくハッピーな出来事に出会ったんだ。 受付の1時間前。 すでに、僕の前に4人ならんでいたんだね。 しばらくして、一番前にいた2人の高校生くらいの男の子が用事を思い出したらしい。 2人は、もぞもぞしてる。 すると、すぐ後ろのおばあちゃんが2人にこう言ったんだ。 「ちゃんと順番取っといてあげるから行っといで」、おばあちゃん2人が行った後、周りの僕たちに「すみませんねえ、2人分、列を空けといてあげて下さい」ってね、何度も、何度も頭を下げてるわけ。 優しそうな、いいおばあちゃんだったよ。 しばらくしてその男の子たちが帰ってきた。 そうして、いきなり主催者のスタッフに、こう聞いたんだ。 「ここ(ロビー)でお茶飲んでいいでしょうか?」 「会場の中はダメですが、ここならいいですよ」 もちろん2人は、自分たちが飲みたかったんじゃない。 カバンの中から、缶のお茶を1つ取り出した。 「あっ・・これ・・飲んで下さい。ほんのお礼の気持ちなんです」 おばあちゃんのために買って来たんだね。 『ここでお茶飲んでいいでしょうか?』 これは、おばあちゃんに対する優しさだった。 もし、飲んじゃいけないお茶を渡してしまったら、それをハダカのまま持ち歩かないといけないからね。 それを気づかったんだ。 でもね、おばあちゃんは、結局そのお茶を最後まで飲まなかった。 いや、嬉しくて飲めなかったんだね。 石黒謙一先生・元気になるおまじない! Vol.24より(本人の許可済み) 10月の岐阜新聞・チラシ状況 10月合計・477枚 平均15.3枚 1.スーパー・98 2.パチンコ・44 3.住宅・28 曜日平均 日・11.5 月・12 火・13 水・12.2 木・20 金・12.75 土・26.5 (なべ) |
|
|
|
|
|
2002
10.24 |
知ったかぶり経済学(2)<コミットメント>/ノーベル賞・235億円?
|
|
知ったかぶり経済学(2)<コミットメント>
近頃どうにもデジカメが欲しくって、家電量販店のチラシを見比べながら、「あれにしよか、これにしよか」と財布と相談しながら悩んでいます。 で、時には実物が見たくなって、お店にも行くんですが、チラシより安い値札がついていることがままあるんですね。 安く買えりゃいいようなもんですが、チラシがあてにならないなら、それを熟読したオレは何だったの? というわけで、そんなややこしいことを、わざわざしているお店の戦略について考えてみました。 ◇◇◇ 自分はこうするぞと宣言することで、相手の選択を制約しようとする行為を「コミットメント」と言います。 例えば、「バーゲンは絶対しない」と言い切ることで、お客に買い控えをさせない場合などが当てはまります。 その際、相手に信用にされなければ、から脅しに終わってしまうので、どれだけリアリティがあるかがコミットメントのポイントになります。 ◇◇◇ 「他店のチラシ価格よりも高ければ必ず値引きします」というのもコミットメントのひとつで、どこよりも安いことを保証してお客を逃がさない戦略に見えます。 でも、うがった見方をすれば、「ライバル店のチラシ価格がうちと同じか1円でも高ければ、積極的に値引きはしませんよ」とコミットしていることにもなるのです。 そういえば、最近の家電量販店のチラシには、「ここから更に値引き」とか「店頭発表」とか、値段が明示されていないものが増えているようです。 ちょっとでも安く買おうとチラシを熟読している消費者は私だけじゃなくって、「他店のチラシよりも・・・」ってのが、実際のところ最安値を保証するものではないこと(=コミットメントにリアリティがないこと)に皆が気付き始めたからでしょうか。(F) ノーベル賞・235億円? ノーベル賞の賞金が235億円ではありません。 島津製作所の株価が急騰して、時価総額が235億円増えた話です。 みなさんご存知の通り、島津製作所の田中耕一さんがノーベル賞をとった事による市場の反応です。 1人の社員が235億円生み出したんです。 まさしく、スーパー社員です。田中さんの記者会見を見ていても、ただの人と言う感じがして、多くのサラリーマンを元気つけたでしょう。 その田中さんが新聞のインタビューに次のように答えています。 Q:研究につきものの失敗をどう考えるか A:「自分もよく失敗し、意気消沈して、もうそこに触りたくないという心境になる。 だが、なぜ失敗したか追求しないと。 例えばある測定で変な値が出たとき、装置のエラーで済ませたら新しい発見はない。 実は装置は正常で変な値が出る何かがあると、と突き止めないと。 「失敗は次に手掛かり」と常に自分に言い聞かせている」 私もつい最近、ある会社の社員研修で、人間だから失敗するんです。 でも、優秀な人は失敗を次のステップにするんですと話をしました。 人は大いに失敗して成長していかなければならないのです。 ただし、同じ失敗は駄目だと思います。 でも、最近の経営者の多くは、その失敗すらないような気がします。 つまり、チャレンジしていないと思います。 成功する経営者はチャレンジしています。 皆様にも大いにチャレンジしていただきたいです。(なべ) |
|
|
|
|
|
2002
10.08 |
最近気になる数字・1000/平等と公平/9月の岐阜新聞・チラシ状況
|
|
最近気になる数字・1000
最近、妙に1,000と言う数字が気になります。 例えば、DMなども、千に三つと言うように千通発送して3件程度仕事に結びつく、私が新入社員研修で講演するときなど、入社後3年間が人生を決まるぐらい大切ですよと話しをします。 これも、約1000日です。それから、起業家も3年頑張れば、仕事が急に増えるなどの話しもあります。 これも約1000日です。私事ですが、ビジネス書、自己啓発の本を1000冊程度読み終えてから、急にいろいろなことが総合的に理解できはじめました。 子供の教育も3つ後の魂100までというように3歳までの躾が非常に大切です。 中学、高校は3年間で約1000日通います。 石の上にも3年とも言われます。これも1000日です。私が思うにこの1000という数字は物事のキーワードとなる数字のような気がします。 経営者の皆さんも、この1000日、1000回を一つのめどにされると目標がたてやすいのではないでしょうか。 3年もまてるかといわれる経営者の方、携帯電話は世の中にいつ出てきたかご存知ですか、万博の1972年ですよ。 それから日進月報改善されてきて現在のように成長産業となったんです。 最近の商品のようですが30年です。コンビニ、マクドナルド、インターネット等、ほとんどが30年です。 1000日ぐらい短いものですね。 1000という数字を意識してみませんか。 そうそう、ちなみに私が会社を設立したとき、DMを700通近く発送させていただき、2件仕事をいただきました。 DMの1000に3って、大体当たっていますよね。(ナベ) 平等と公平 先日参加したセミナーで、平等と公平を履き違えないようにというお話がありました。 私たちは、幼いころから「人はみな平等・公平である」と教わってきました。 特に平等と公平の使い分けを考えず、同じように使っていたように思います。 辞書で調べてみると、「平等・・・差別しないで、みな同じな様(さま)」、「公平・・・見方が公正でどちらにも偏らないこと」となっています。 これまでは本当に平等だったのでしょう。 やってもやらなくても同じ。 一生懸命やる人も、そうでない人も同じ待遇。 これはいわゆる不公平なのではないでしょうか。 これからは、公平な、正確な評価のされる時代が来ると言われます。 本当の意味の競争社会が来ます。(この穏やか日本においてどこまでそうなるか、楽しみなのは私だけでしょうか) これを大変と思うか、チャンスと思うかは、人それぞれだと思います。 しかし、今はとりあえず、どう思うかよりも、まずこの事実をしっかりと認識して、危機感を感じなければ、と思う私も、まだまだ平和ボケしているのでしょう。(あん) 9月の岐阜新聞・チラシ状況 9月合計・420枚 平均14枚 1.スーパー・79 2.パチンコ・33 3.住宅・24 曜日平均 日・13.75 月・5 火・14.75 水・13.25 木・17 金・12.75 土・28.5 |
|
|
|
|
|
2002
09.24 |
知ったかぶり経済学(1)<逆選択>/救命ボートの知恵
|
|
知ったかぶり経済学(1)<逆選択>
例えば、ある自動車ディーラーが、新車販売時のオプションとして、誰でも決められた金額を払えばメーカーが保証するよりも長期間、修理費用をカバーするという商品を売り出したとします。 さて、どんな人がこの商品を購入するでしょうか? そして、ディーラーは儲けることが出来るでしょうか? おそらく、この商品を購入するのは、走り屋だったり、遠距離を走ったり、通常よりも苛酷な乗り方をするため、自分は修理を受けることが多いと考えるドライバーに偏るでしょう。 その結果、予想した以上に修理費用がかさみ、それを補填するためにディーラーは料金を引き上げなければなりません。 するとさらに、高い料金を払ってもメリットが得られる人ばかりが残り・・・と結局、この商品は成り立たなくなってしまいます。 このような、取引を行う際に、売手と買手の間に情報格差がある(この例では、ディーラーはドライバーの走り方を知りません)ために生じてしまう現象を、経済学の用語で「逆選択(アドバース・セレクション)」と呼びます。 「逆選択」は、もともと保険分野で生まれた考え方ですが、企業が人件費を抑えるために、社員一律で賃金カットをした結果、他の会社に移っても今以上の給料が取れる有能な社員ばかりが転職してしまったというような皮肉なケースにも当てはまります。 つまり、意図した結果とは逆の選択を呼び込んでしまうような状況を指すわけですが、さて、あなたの会社の商品(サービス)や経営方針は、取引先や従業員の「逆選択」を引き起こすようなしくみになっていませんか? (F) ※ このコーナーでは、ちょっとしたネタに、そして少しは経営にも役立つ経済学のキーワードをご紹介していきたいと思います。 救命ボートの知恵 「海からも空からも救助の手はさしのべられている。 望みを捨てずにがんばろう」9月のはじめに、ある方の好意によりヨットに乗せていただきました。 ヨットは20トンあり、世界を航海しているすばらしいものでした。 久しぶりにゆったりとした時間をすごす事ができました。 その時、救命ボートの講習会があり、そこでいろいろなことを学びました。 まず生命がかかっているだけに非常に考えられています。 雨の水がためれる仕組み、ボートが安定できるようにボート下に袋があること、そなえつけナイフの先が丸くしてあること。 ボートが海面に開いたときすぐに戻せる仕組み、そのた、細かい事が沢山あり人間の知恵を感じました。 しかし、問題は生死の時に落ち着いた行動をできるかが大きな問題だと思いました。 講習が終わったときに小さい紙がでてきたのでした。 それが上の救助の事が書いてある紙でした。 私は、この紙こそ大きくしてすぐに目にとまるような仕組みが必要だと思いました。 でも、経営にていませんか、経営者の成功されたかたは、必ずいいます、成功の秘訣は、望みをすてずに頑張り、最後まであきらめないこと。(ナベ) |
|
|
|
|
|
2002
09.08 |
運輸業からサービス業へ/社長の給料/個人判断能力の低下/8月の岐阜新聞・チラシ状況
|
|
運輸業からサービス業へ
ご存知、タクシー業界の話です。 景気に左右される業種の一つですが、企業努力には、本当に頭が下がります。 価格競争はもちろん、基本的な接客マナーの向上。 ペットも大丈夫な車、ベンツなどの高級車さらには、介護タクシーなど次から次へあります。 経営改革にが、非常に見習う点が多くあります。 また、こんな話を聞いたことがあります。 携帯電話に自分に直接連絡を下さいと営業してみえるかたがいると、その方は、非常に親切でサービスがいいとのことで、非常に忙しいと聞いたことがあります。 サービスは会社全体で向上させることがきでますが、感動のサービスは最終的には人にかかっています。 そういう意味では会社全体が高いサービスを目指し、個人もさらに努力をしないと企業は生き残れないかもしれません。 私も人にはいろいろいいますが、自分の会社がといわれると困ります。 が、社員研修では徹底的に笑顔と挨拶の練習をしています。 先日もある会社の社員研修で、「あいさつ」というてーまでセミナーをさせていただきました。 たかがあいさつ、されどあいさつ、ただし、今現在、世の中で業績のいい会社は間違いなく大きな声で元気よくあいさつされます。 このあたりに業績回復のキワードがあるのではないでしょうか(ナベ) 社長の給料 8月下旬の新聞に米国を除く主要企業50社のトップについて2001年の年収関する調査結果の新聞記事がありました。 日本のトップは、ソニーの出井伸之会長の180万ドル(約2億1千万円)、トヨタ自動車の奥田会長は50万ドル(6千万円)。 その他、日本の大手企業の経営者の収入は、情報提供が不十分との事。 ちなみに、1位はカンニングフォック代表の1300万ドル(約15億3千万円)です。 社長の給料どれくらいが適当かはいろいろ言われますが、私個人の意見は、法人にある程度利益がでていれば、1億円はとってもいいと思います。 私も1億円とは言いませんが、サラリーマン時代の収入の3倍はとれるように頑張りたいです。 (ナベ) 個人判断能力の低下 「自分の家で食べる野菜は別で作ってますよ。こんなに農薬使った野菜、食べたくないですからね。」 ある知り合いの農家の方から聞いた話です。 ここのところ次々に発覚する食品偽装問題。 「恐ろしい世の中になったものだ。」と言われます。 しかし、どうでしょう。 これまでにもきっとあったこと、あったけど、隠していたことだと思います。 私は、むしろ、真実が世の中に知らされるという、「なんていい時代になったのだろう。」と思いました。 しかし、このようなことが発覚したのも内部告発からでしょう。 今、審議されているメディア規制法案が成立すると、人を守るために作る法律が、人を犯す可能性のある真実を隠すこともありえるはずです。 もちろん共存するためには、決まりは大切です。 しかし、ここまで決まりを作らないと秩序の守れない社会、個人の道徳判断を信用できない社会。 エスカレートする一方なのでしょうか。(あん) 8月の岐阜新聞・チラシ状況 8月合計・380枚 平均12.6枚 1.スーパー・81 2.パチンコ・40 3.住宅・21 曜日平均 日・9.25 月・8.5 火・12.25 水・10.75 木・15.4 金・10.6 土・17.4 |
|
|
|
|
|
2002
08.24 |
運輸業からサービス業へ/非常識な成功方法(神田昌典著書)を読んで/少子化問題のヒント
|
|
運輸業からサービス業へ
ご存知、タクシー業界の話です。 景気に左右される業種の一つですが、企業努力には、本当に頭が下がります。 価格競争はもちろん、基本的な接客マナーの向上。 ペットも大丈夫な車、ベンツなどの高級車さらには、介護タクシーなど次から次へあります。 経営改革にが、非常に見習う点が多くあります。 また、こんな話を聞いたことがあります。 携帯電話に自分に直接連絡を下さいと営業してみえるかたがいると、その方は、非常に親切でサービスがいいとのことで、非常に忙しいと聞いたことがあります。 サービスは会社全体で向上させることがきでますが、感動のサービスは最終的には人にかかっています。 そういう意味では会社全体が高いサービスを目指し、個人もさらに努力をしないと企業は生き残れないかもしれません。 私も人にはいろいろいいますが、自分の会社がといわれると困ります。 が、社員研修では徹底的に笑顔と挨拶の練習をしています。 先日もある会社の社員研修で、「あいさつ」というてーまでセミナーをさせていただきました。 たかがあいさつ、されどあいさつ、ただし、今現在、世の中で業績のいい会社は間違いなく大きな声で元気よくあいさつされます。このあたりに業績回復のキワードがあるのではないでしょうか(ナベ 非常識な成功方法(神田昌典著書)を読んで 8月下旬の新聞に米国を除く主要企業50社のトップについて2001年の年収関する調査結果の新聞記事がありました。 日本のトップは、ソニーの出井伸之会長の180万ドル(約2億1千万円)、トヨタ自動車の奥田会長は50万ドル(6千万円)。 その他、日本の大手企業の経営者の収入は、情報提供が不十分との事。 ちなみに、1位はカンニングフォック代表の1300万ドル(約15億3千万円)です。 社長の給料どれくらいが適当かはいろいろ言われますが、私個人の意見は、法人にある程度利益がでていれば、1億円はとってもいいと思います。 私も1億円とは言いませんが、サラリーマン時代の収入の3倍はとれるように頑張りたいです。 (ナベ) 少子化問題のヒント 少子化問題で、国は大変困っています。 それにともない経済も大きな問題がでてくるでしょう。 そんな解決策のヒントを偶然インターネットで見つけましたのでご紹介いたします。 実は、「女性の社会進出度合いが高い国では、子供がたくさん生まれる」という北欧、米国の傾向です。 日本では、女性の高学歴化と社会進出が少子化へつながるとの見方が依然強いですが・・・・ では、北欧のデンマークでは、少子化対策ではなく、労働力対策として、女性の労働力を労働市場にだすために、保育園、幼稚園を増設したことが結果的に少子化対策になったのかも、そういえば、アメリカはベビーシッタがあたりまえ、日本では、まだまだですね。 日本の少子化問題も、そこにメスをいれれば随分変わるのでは? 実は当社は、「中小企業は優秀な人が採れない」という声を聞き、優秀で働いていない主婦を週2日~3日派遣しようと思いはじめました。 そうすれば企業側の人件費の負担も少なく、かつ優秀な人を確保できると思いましたが、まだまだ中小企業側にそういう考えがないみたいです。 ところが、ある大手企業さんが、それはいい考えとの事で、ただ今内部で仕事量、指示の問題を検討していただいています。 中小企業にメリットのある仕組みを考えたのに、結局いち早く声をかけていただいたのが大手企業でした。 大手の弛みない努力は、中小企業は見習うべきだと思います。(ナベ) |
|
|
|
|
|
2002
08.08 |
当たり前の事は当たり前に/女性が主役/夫婦喧嘩の祠
|
|
当たり前の事は当たり前に
トヨタ自動車の人材育成の研修に参加しました。 印象に残ったのは、先輩が後輩を指導している話です。 これは、当たり前ですが、実はできていない会社が多数です。 当たり前の事を、当たり前に出来る会社が非常に強いんだと改めて実感しました。 現在、大企業も非常に厳しい状況です。 トヨタさんも、今後3年間で原価3割ダウンを発表しています。 強い企業ほど積極的に動きます。勝っていって当然です。(ナベ) 女性が主役 経営コンサルタントの神田先生が書かれた本です。 内容はいたって常識が書かれています。 この常識は成功するための常識で、一般の人からすれば、非常識なのかもしれませんね。 何が書かれているかと言えば、「目標を紙に書き、朝晩眺める」「読書をする」「講演のテープを聞く」「金持ちの人と付き合う」その他いろいろ書いてあります。 私が実行していなかったのは、講演のテープを聞くことでした。 さっそく知人の社長に借りて聞いています。 そういえば、独立してから、桁外れのお金の話をする社長様に何人かお会いました。 その時の感想は、お金がお金を生むんだなとつくづく思いました。経営者、会社の幹部の方ぜひ読んで下さい。(ナベ) 夫婦喧嘩の祠 古のローマには、夫婦喧嘩の神というのがあったそうです。 夫婦喧嘩の祠では、2人同時に話してはならないという決まりがあります。 そのため、自然と、夫が不満を言っている間は、妻は耳を傾け、逆に妻が不満を言っている間は、夫は耳を傾け・・・相手が言い終えるまで、決して口を挟んではならない。 すると、不思議と夫婦喧嘩は治まり、夫婦は仲直りをして帰るといいます。 これは夫婦のみならず、人間関係すべてに言えるのではないでしょうか。 デジタル社会である今、オーラル・コミュニケーション能力の欠けた現代人には最も必要なものの一つかもしれません。(「ローマは一日にしてならず」塩野七生著より) |
|
|
| バッグナンバーTOP |
HOME |
|
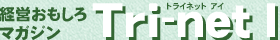
 お問合せ
お問合せ